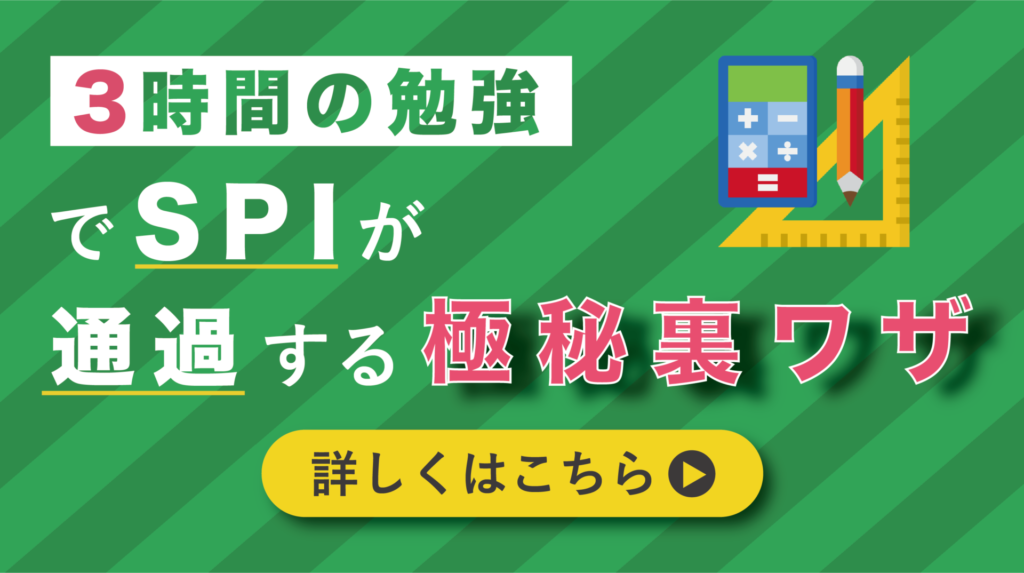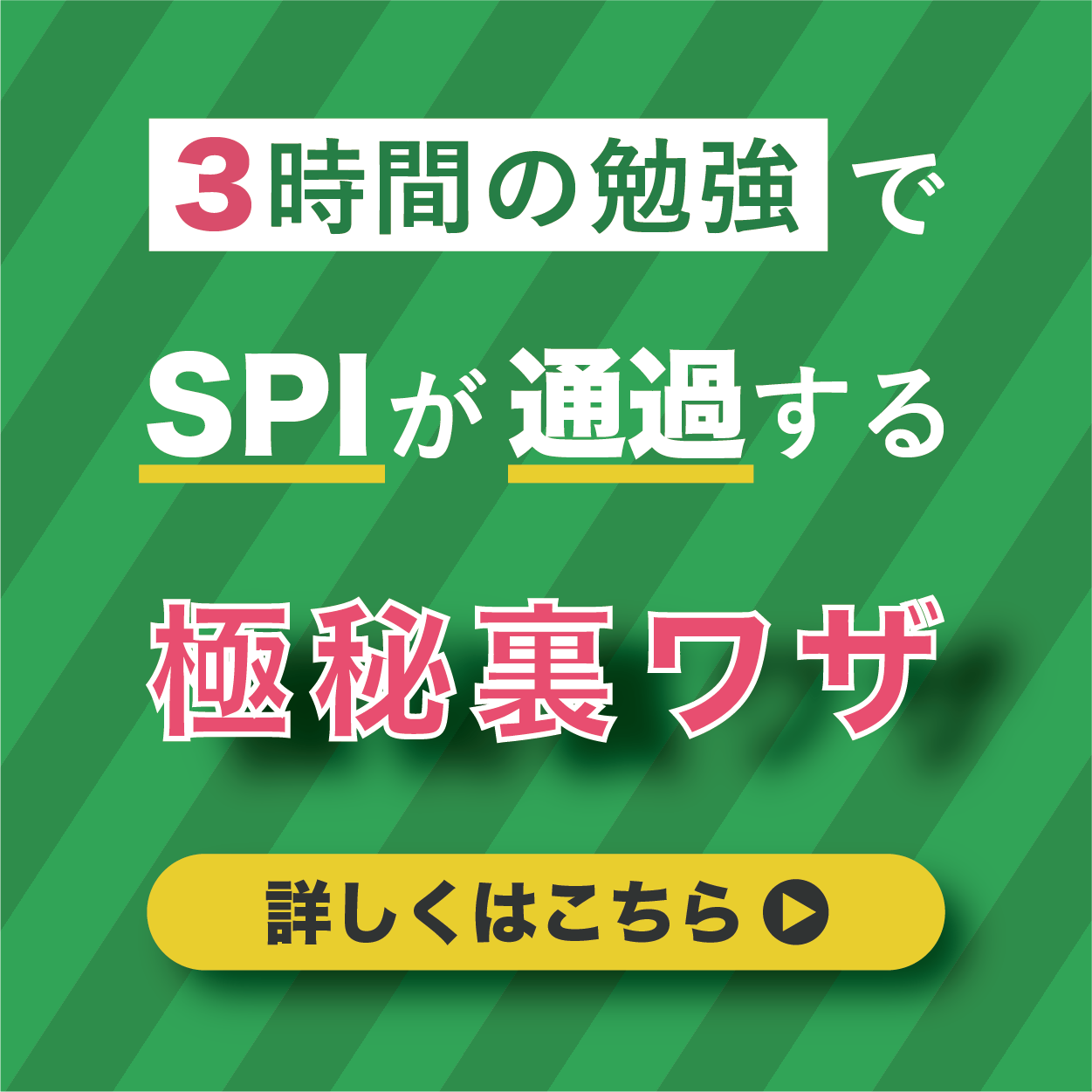SPIでわからない問題が登場したとき、適当に思いつく回答をして次の問題に進んだ方がいいのか、回答せずに次の問題に進んだ方がいいのか迷っている人も多いかと思います。
※「SPIとは?対策方法や問題・例題をすべて紹介!適性検査SPIはこれで完璧だ!」もぜひ合わせてご覧ください。
後ほど詳しく解説しますが、SPIは誤謬率が計測されないWEBテスト(適性検査)なので、わからない問題があったときは適当に回答して次の問題に進むのが得策です。
本記事では、SPIについて日本トップレベルに熟知しているSPIマスターの私カズマが誤謬率とは何かについて解説した後、SPIと誤謬率の関係や誤謬率が計測されるWEBテストはあるのか?などについて解説していきます。
SPIを受検予定の就活生や転職活動中の社会人はぜひ参考にしてください。
ちなみにですが、SPIにはたった3時間の勉強でSPIが通過してしまう勉強法があります。
これさえあれば限りなく少ない努力で内定に大きく近づきます。
これは私が100回以上ものSPI受検を通して生み出した、どの本にも載っていない超コスパの良い究極の勉強法です。
興味のある人はぜひ以下のボタンからその方法をチェックしてみてください。
SPIにおける誤謬率とは?
誤謬率(ごびゅうりつ)という言葉を初めて聞いた人も多いかと思うので、まずは誤謬率とは何かについて解説します。
誤謬率とは回答数に対する不正解の割合のことです。例えば100問の問題に回答し、不正解の数=30問の場合、誤謬率は30%となります。
誤謬率が計測される(=考慮される)テストの場合、問題を間違えるごとに点数に影響が出てしまいます。なので、例えば全部で10問あるテストにおいて
- 受検者A君=10問全てに回答し、3問正解・7問不正解
- 受検者B君=10問中5問だけ回答し、2問正解・3問不正解(残り5問は未回答)
だった場合、正解数はA君の方が多いにも関わらず、点数はB君の方が高くなったりします。
つまり、誤謬率が計測されるテストではわからない問題は無理に回答しない方が良いということになります。
逆に、誤謬率が計測されないテストではわからない問題が登場しても適当に回答する・勘で回答するのが得策ということになります。正解数をなるべく増やすことに注力しましょう。
SPIでは誤謬率が計測されない
では、SPIでは誤謬率が計測されるのでしょうか?結論から申し上げますと、SPIでは誤謬率は計測されません。
実際にSPIの受検画面においても「誤謬率が計測されます」といった注意書きは一切ありません。
なので、SPIでわからない問題が登場した場合は適当に回答したり・勘で回答したりして次の問題に行くのが得策です。
特にSPIの言語(国語)においては選択肢の中から答えを選ぶ問題も多いため、適当・勘で回答しても正解する可能性は十分にあります。なので、未回答のまま次の問題に進むことは絶対に避けましょう。
※選択肢が4つ用意されている場合、適当・勘で回答しても正解する確率は1/4(25%)もあります。
ちなみにですが、SPIの非言語(数学)では選択肢の中から答えを選ぶ問題はほとんど出題されません。
自分で答えの数字を入力する問題がほとんどなので、非言語(数学)の場合は残念ながら勘で回答しても正解する可能性は低いです。
「SPIの非言語(数学)を完全解説!対策方法やできない人でも点数を上げる方法!問題もご紹介」もぜひ合わせてご覧ください。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
誤謬率が計測されるWEBテスト(適性検査)はある?見分け方は?
SPIでは誤謬率が計測されないことがわかりましたが、SPI以外の多くのWEBテスト(適性検査)においても誤謬率は基本的には計測されません。
なので、就活や転職活動においてWEBテスト(適性検査)を受検する際には不正解の数は気にせず、なるべく多くの正解を目指しましょう。
しかし、事務職や経理職向けのWEBテスト(適性検査)では稀に誤謬率が計測される場合があるので注意が必要です。
※事務職や経理職は職種の特性上「ミスをしない」というスキル・能力が求められる傾向にあるため。
自分が受検するWEBテスト(適性検査)が誤謬率を計測しているかを見分ける方法ですが、誤謬率を計測する場合、受検前にその旨が知らされるケースが大半です。
例えば、事務職向けの適性検査として事務職適性検査[FT型]というWEBテストがありますが、このWEBテストでは誤謬率が計測されています。
そして、事務職適性検査[FT型]のホームページには以下の記載があります。
事務職とは、正確さが非常に重要な職種です。お金の計算など、決してミスが許されない仕事が中心になります。処理の速さももちろん望まれますが、それ以上に正確さが必要とされます。そこで、事務職適性検査では、「誤謬率(ごびゅうりつ)」を用いて処理の正確さも測定します。
おそらく、受検前の注意点などを記載した画面などでも誤謬率が計測される旨が記載されているかと思います。
また、昔に存在していたSPI-R、SPI-NというWEBテストでも誤謬率は計測されていました(SPI-R、SPI-Nは現在は廃止されています)
SPI-R、SPI-Nは共にSPIの一種で、SPI-Rは大学生・短大生を対象とした一般職採用で使われることが多かったWEBテストです。
SPI-Nは短大生・高校生を対象とした一般職・事務職・技能職採用で使われることが多かったWEBテストです。
※SPIの種類について解説した記事もご用意しているのでぜひ合わせてご覧ください。
現在はほとんどのWEBテストにおいて誤謬率は計測されていませんが、事務職や経理職、一般職の選考で用意されているWEBテストを受検するときだけは誤謬率が計測されるかどうかをしっかりと事前に確認しておきましょう。
誤謬率が計測されるかどうしてもわからない・知りたい場合は採用担当者に直接メールなどで聞いてしまうのも一つの手段です。
その場合は以下のようなメールを送付すると良いでしょう。
株式会社〇〇
〇〇様
お世話になっております。貴社の選考を受けさせていただいている〇〇です。
貴社の選考フローでWEBテスト(適性検査)の受検が用意されていますが、このWEBテストでは誤謬率が計測されますでしょうか?
貴社への志望度が高く、なるべく高得点を取りたいと思っていますので、もし誤謬率が計測される場合、わからない問題は無理に回答するのは控えようと思っております。
可能でしたら教えていただけますと幸いです。お手数ですが、ご確認よろしくお願いいたします。
※あくまでも一例となります。
(志望度が実際にはあまり高くなくても)志望度が高いと伝えることによって採用担当者も「この人を通過させたい」と思うようになり、その結果として誤謬率を計測しているかどうかを教えてくれるかもしれません。
メールを送付した結果、「誤謬率を計測しているかどうかについては教えることができません」と返信が来た場合は素直に諦めましょう。
しかし、上記でも解説した通り、ほとんどのWEBテストにおいては誤謬率は計測されていないのでそこまで心配する必要はありません。
🔽 本にも載ってない極秘情報 🔽
いかがでしたか?
今回は誤謬率とは何かについて解説した後、SPIで誤謬率は計測されるのか?や誤謬率が計測されるWEBテスト(適性検査)はあるのか?などについて解説していきました。
WEBテストでは基本的に多くの問題に正解することが高得点に繋がります。選択肢の中から答えを選ぶ問題が多いWEBテストでは特に、未回答のまま次の問題に進むことは絶対に避けましょう。
※SPIでは性格検査で未回答が多いと再受検になるケースがありますのでご注意ください。詳しくはSPIは未回答でも大丈夫なのかについて解説した記事をご覧ください。